創世記22章1~19節 年十二回で学ぶ創世記 イサクの燔祭
イサクの燔祭は西洋絵画の題名にもなっていますが、漢語的、文語的表現です。新共同訳聖書では「焼き尽くす献げ物」と意訳されています。献げ物(いけにえ)の種類や翻訳の違いについては新共同訳聖書巻末にある用語解説の27ページ献げ物の項目に詳細が載っています。また、来週の説教の中で仔細解説します。
神様はアブラハムとサラの間に養子ではなく実子として、跡継ぎの子が生れると創世記17章で約束されていました。事実創世記21章でアブラハム100歳、サラ90歳の時に生れた子どもです。しかし、神様は22章でそのひとり子、年より子であったイサクを人身供養としてささげなさいとおっしゃいました。アブラハムはもだえるほど悩んだでしょう。神さまの計画の全容がわからなかったでしょう。しかし、神の計画の全容がわからないし、自分のささげる礼拝と神様のご計画のつながりもわからないけれども自分に超高齢にして実子を与えてくださった神様にできないことはないと思って神様に信頼し、イサクをいけにえにささげようとします。結果、アブラハムの見上げた信仰を見た神様は感服し、アブラハムにイサクをいけにえとしてささげることを禁じました。この間3日間ありました。
この出来事が元になって、ユダヤ教、キリスト教は絶対に人心供養を禁じます。人の命をなによりも重んじる宗教になりました。
また、行いではなくて信仰により救われること。いけにえとなる存在が生れないはずの夫婦から奇跡的に生れる。高齢出産、父が子を自ら手にかけて、いけにえにささげようとする、3日目に自体が急転好転する。これって全て新約聖書のイエスキリストの誕生とイエスキリストの十字架による救いとうり二つなのです。またこのモリヤの山の岩の上にエルサレムの神殿が建てられます。
表紙の口絵にある岩のドームがある場所です。岩のドームの岩とは、アブラハムがイサクをささげようとしたその岩なのです。神様は聖書の中で、救いが確かにわかるように、この救いこそが神が提示された唯一の救いであることがはっきりとわかるように、歴史をとおして「韻を踏み」ます。しかも、同じ場所で、アブラハムは天国からキリストの十字架を見させられた時、痛いほど御父なる神様の御心がわかったはずです。
※サムネイルは岩のドーム(ウィキペディアより)

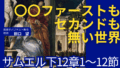

コメント