チ。原作8話を神学してみた。そもそも占星術ってOKだったの?
はじめに
原作8話の第二集P65ページにおいて、アニメ5話において、グラスとオクジーは石箱を発見し、異端者の手紙を発見します。その中で異端者がもともと占星術師として生きてきたことが明かされています。チの物語の中では地動説が異端の学説とされ大問題になっていますが、実際の歴史の中では、地動説うんぬんよりのそもそも占星術の方が異端とされるような大問題だったのです。そこで、今回は中世ヨーロッパにおける占星術の位置づけについて神学してみたいと思います。
聖書は明確に「占い」を禁止しており(申命記18章、レビ記19章など)、旧約・新約を通じて「人が未来を知ろうとする試み」は神への信頼に反するものとして扱われてきました。しかし、中世ヨーロッパにおいては占星術(astrologia)が盛んに行われ、王侯貴族の宮廷に仕える占星術師も少なくありませんでした。大学においても天文学と不可分な学問として扱われ、医療や農耕の分野でも応用されました。では、なぜ「占い禁止」を掲げる聖書の伝統と、占星術の流行とが矛盾なく共存できたのでしょうか。本稿では、聖書的背景を踏まえた上で、中世における占星術の評価と、その神学的な位置づけを考察します。
1. 聖書における占い禁止の伝統
1.1 旧約聖書の規定
旧約聖書は繰り返し「占い」「まじない」「口寄せ」を禁じています。
-
レビ記19:26 「占いをしてはならない。まじないをしてはならない。」
-
申命記18:10-12 「占い師、呪術師、魔術師、口寄せなどはあなたのうちにあってはならない。これらのことをする者は皆、主に忌みきらわれる。」
これらの背景には、イスラエルの民が周囲の異教的文化(バビロニアの星占いや、カナン人のまじない)に取り込まれる危険があったことがあります。旧約の預言者たちは、人間が未来を知ろうとする行為は神の主権を侵害するものであり、真の知恵は神の啓示にのみ由来すると強調しました。
1.2 新約聖書における展開
新約聖書でも「占い」は否定的に扱われます。使徒言行録16章16節には「占いの霊に取りつかれた女奴隷」が登場し、パウロがその霊を追い出したと記されています。ここで占いは悪霊と直結しています。さらにヨハネ黙示録では「魔術を行う者たち」が神の国から排除されると記され(黙示録22:15)、終末論的視点においても占いは禁止事項に含まれます。
このように、聖書全体において占いは一貫して「偶像崇拝」や「悪魔的行為」と結びつけられ、神を信頼せず自ら未来を操作しようとする人間の罪とみなされたのです。
2. 占星術の中世的展開
2.1 自然占星術と判断占星術の区別
中世において「占星術」は一枚岩ではなく、しばしば二つに区別されました。
-
自然占星術(astrologia naturalis)
星の運行が季節や気候、人体に影響を与えるとする学問的研究です。農耕暦や医療の診断に活用され、実用的・自然科学的な要素を含むため正統に認められました。 -
判断占星術(astrologia iudiciaria)
星の配置から個人の運命や未来を直接占うものです。自由意志や救済論に抵触する可能性があり、しばしば批判の対象となりました。ノヴァクさん出番です!
この区別によって、中世社会は聖書の「占い禁止」を直接破らずに占星術を部分的に受け入れることができました。
2.2 宮廷と大学における占星術
王侯貴族はしばしば専属の占星術師を抱え、戦争や結婚、政治的判断の参考にしました。大学においても、天文学と占星術は不可分の学問であり、医学生は患者の出生図をもとに病因を診断することが推奨されました。修道院でも農作業や暦の作成に占星術的知識が用いられました。
3. 神学者たちの議論
3.1 アウグスティヌスの批判
教父アウグスティヌスは『神の国』第5巻で占星術を強く批判しました。彼は、双子の兄弟が同じ星の下に生まれても異なる運命をたどることを指摘し、星が人間の生涯を支配するという考えは虚偽であると論じました。また、それは人間を罪から解放し、自由意志と責任を否定する危険があるとしました。アウグスティヌスにとって、占星術は「悪魔の惑わし」であり、聖書の禁止規定に沿って断罪されるべきものでした。
3.2 トマス・アクィナスの折衷的理解
一方で、13世紀のトマス・アクィナスは占星術を全面否定せず、「星は物質界に影響を与えるが、人間の霊魂の自由意志を強制はしない」と述べました。つまり、星は気質や傾向に影響を与え得るが、最終的に善か悪を選ぶ責任は人間にあると考えたのです。この解釈は、聖書の「占い禁止」を維持しながら、自然占星術を学問として正当化する重要な論理となりました。
3.3 1277年のパリ大学における禁止
1277年、パリ司教ステファヌス・タンピエは219項目の学説を異端的誤謬として断罪しました。その中には「星が人間の意志を必然的に決定する」という占星術的決定論が含まれていました。これはまさに聖書の「占い禁止」と響き合うものであり、神学と学問の境界線を画する出来事となりました。
4. 聖書と占星術の「折衷」的共存
4.1 禁止規定の解釈戦略
聖書の禁止規定は、「未来を断定的に予知する行為」への批判として解釈され、自然界の秩序を観察する学問的占星術はこれに含まれないとされました。すなわち、聖書における「占い(divinatio)」は悪霊や偶像崇拝と結びつく行為であり、「自然の徴候を読むこと」とは区別されると理解されたのです。
4.2 実用面での必要性
医療や農業において、天体の運行を無視することは不可能でした。中世の人々にとって、月の満ち欠けや惑星の動きは自然のリズムを知る手がかりであり、これを「神の創造秩序を探る行為」と理解することは十分可能でした。このため、聖書的禁止と矛盾しない範囲での活用が認められました。
4.3 信仰と知のバランス
中世の教会は、占星術を全面的に拒絶するのではなく、「自由意志と神の主権を侵さない限り許容される」という立場を取りました。これは聖書の権威を守りつつ、学問と社会的実用を調和させる中世的知恵であったといえます。そう、日本文化は白黒はっきりつけないあいまいな文化で、西洋は白黒はっきりつけたがると言われることが多いですが、欧州においても鷹揚な世界観があったのです。
結論
聖書は占いを厳しく禁じており、その根本には「神以外のものに未来を求めてはならない」という信仰の原則があります。中世ヨーロッパにおいても、この原則は決して無視されたのではなく、「未来を断定する占星術は異端」とされ続けました。他方で、自然の秩序を読み取り、農業や医療に役立てる「自然占星術」は許容され、神の創造秩序を探る学問と位置づけられました。
したがって、中世における占星術の歴史は「聖書の禁止規定と折り合いをつけようとした試みの歴史」であったといえます。アウグスティヌスの厳しい批判と、アクィナスの折衷的解釈、そして1277年の禁止令はその象徴的な出来事でした。結局のところ、中世の人々は聖書の権威を尊重しつつも、自然の知識を探求する道を模索し続けたのであり、その知的葛藤の中にキリスト教文明の豊かな姿を見いだすことができるのです。マンガ、チの作者魚豊先生もおそらくそのへんの事は重々承知していらっしゃると思いますが、物語の中心点がぶれないように占星術に関する欧州の葛藤に関する歴史はわざと触れられていないのだと思われます。
ちなみに、現代においてはプロテスタント教会はアウグスティヌスの解釈に回帰して、占いの類は私も含めて一切しない人が多い。


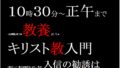
コメント