ルカの福音書22章35~38節「二振りの剣 イエスは武力を肯定されるのか?」
本日のテキストは歴史的には「両剣論(theory of two swords)」と言われ、カトリック教会では教皇権と皇帝権をあらわす淵源として捉えれてきました。また、ある解釈者はルカの9章真逆のことをイエス様がおっしゃっているので弟子たちを試すためにカマをかけていると解釈する人もいます。さらには、38節の「それでよい」「十分である」は日本語の「結構」のようにyesともnoとも取れる言葉でこの段落の解釈を難解にさせています。
日本のキリスト教界では非戦論が多数派を占めているので、実力行使を肯定されていないと読む方がカッコいいのでしょうし、ウケもいいのでしょう。そのように言葉通りに剣の必要性を解いたと読めないその背景にはイエス様は絶対に実力行使を肯定されないという前提、読み込みがあるのではないでしょうか?しかし、現代日本のキリスト教界が作った虚像であって、聖書が示すイエス様の実像は、宮清めのシーンでは鞭を用いて、神殿を盗人の巣窟にするなと烈火のごとく怒り、暴れまわられた。ルカの14章31節では、平然と戦争をたとえに用いています。マタイ26章53節では天から軍勢を派兵して制圧することについて言及していますし、実際、黙示録19章ではその天の軍勢を率いて圧倒的武力、圧倒的実力の前に最後の最後まで神の呼びかけを拒み続け、逆らい続ける者を踏みつぶし、蹴散らし、肉片と化してしまう姿さえ描かれています。イエス様がルカの福音書22章で嘆いておられるのは次のオリーブ山でのお祈りもそうですが、目の前に危機が迫ってきているのに、どうしようもないほど危機感がないことです。文脈からよめば、弟子たちが男13人を守るのに立った二振りの剣で事足りるという楽観に対し、あきれて議論を打ち切るために「それでよい」「十分だ」とおっしゃられたのです。
※サムネイルはエドゥアルト・シュヴォイザー作「カノッサでのヘンリー王」


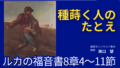
コメント