ゼファニヤ書2章1~7節 聖書の中のパレスチナ問題
パレスチナというのは「ペリシテ人の地」の意味です。ゼファニヤ書にもガザやペリシテの名が出てきます。ペリシテ人とはサムエル記で契約の箱を一時奪った民であり、ダビデ王のお話しに出てくるゴリアテや士師記のサムソンのお話しに出てくるデリラがペリシテ人です。海の民とも呼ばれエーゲ海(ギリシャ)の方からやってきて中東にブドウの栽培や鉄器などをもたらした民族です。非常に強力な民族で約束の地の海岸平野に根拠をおき、それが為にイスラエル民族が山岳民族のように山に追われ、聖書の神様が当時中東では「山の神様」と誤解されるほどでした。では、現代のパレスチナに住む人がペリシテ人が同じかと言えばそうではありません。ゼファニヤの預言から数十年後、ペリシテ人はバビロンに併合された後、周辺民族と同化し、歴史の表舞台からいなくなります。存在しもしない、ペリシテ民族なのになぜパレスチナと呼ばれるのか?イエス様も預言されていたユダヤ戦争(ユダヤとローマの戦争)が紀元70年と、紀元135年第二次ユダヤ戦争(バル・コクバの乱)が起き、第二次ユダヤ戦争を鎮圧したローマ皇帝ハドリアヌスがユダヤ州をシリア・パレスチナ州と改名してしまいました。その後、イスラム化アラブ化がおきて、今パレスチナ人と呼ばれているのは、パレスチナ自治区に住んでいるアラブ人のことです。英国が当該地域をアラブともユダヤとも呼ぶのを避けようとして、忘れられていた古代の名称を採用したのです。ただ、このアラブ人もアブラハムの子イサクの異母兄イシュマエルの子孫であって聖書の中では祝福と反映が約束されて民でもあります。 ゼパニヤ書は直接的には、エルサレムや周辺諸国がバビロンによって滅ぼされることが語ります。しかし、その一方でその征服者をバビロンだけに固定せず、メシヤの到来(私たちにとっては再臨)のことを語っています。それは、ルカ13章34~35節で
エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に遣わされた人々を石で打ち殺す者よ、めん鳥が雛を羽の下に集めるように、わたしはお前の子らを何度集めようとしたことか。だが、お前たちは応じようとしなかった。 見よ、お前たちの家は見捨てられる。言っておくが、お前たちは、『主の名によって来られる方に、祝福があるように』と言う時が来るまで、決してわたしを見ることがない。」
ルカの福音書 13章34,35節
イエス様が語ったことでもあり、また、黙示録に書かれている終末にも合致します。異邦人の私たちからすればメシヤは救い主として、初顔合わせしたのですが、実は裁き主としても、預言されており、それが再臨の主であるという救済史の青写真を改めて知っておきましょう。
サムネイルはアンソニーヴァンダイク作「サムソンの捕縛」

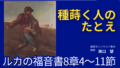
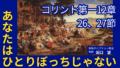
コメント