ルカ福音書8章4~11節 種蒔く人のたとえ
読書好きの方は、岩波書店のマークを思い浮かべることでしょう。岩波書店のHPには「創業者岩波茂雄はミレーの種まきの絵をかりて岩波書店のマークとしました.茂雄は長野県諏訪の篤農家の出身で,「労働は神聖である」との考えを強く持ち,晴耕雨読の田園生活を好み,詩人ワーズワースの「低く暮し,高く思う」を社の精神としたいとの理念から選びました.」とあります。そのミレーの種蒔く人にもエピソードがあります。ある日ミレーがパリを散歩をしていると、美術商の店先に掛けてある彼が売った裸婦画を二人の男が眺めているのに出くわしました。 「この絵は誰が書いたんだい?」 「ミレーって男さ」 「ミレー? どんな絵描きだい?」 「いつも女の裸ばっかり描いていて、それしか能のないやつさ」二人の男はそう会話して立ち去っていきました。 それを聞いていたミレーは愕然としました。お金の為に仕方なくとは言えども、裸婦画ばかり書いているせいで、世間に低級な好みを狙っている画家であると評価されているのだと知ったからです。以後、彼は一切裸体画は書かない、と心に決めたといいます。そこで書かれたのが、本日扱う『種蒔く人』です。農民の絵であると同時に、聖書の本日のテキストをモチーフとしています。 このたとえ話の第一は、悪魔の罠にはまって折角の御言葉も身につかずじまいになる人。第二は、苦しくなると放り出せばいい位にしか福音に本当は感動しなかった人。第三は、世俗の誘惑と吊りあってそこそこ位にしか位にしかイエス様の持って来られたものがありがたくない人。……こういうケースは全て、福音の宣言が無駄になる。といいます。しかし、無駄にならないこともありますそれは、イエスが望まれた正しい受け止め方で受け止めた人です。「この罪ある私を生かすのはイエス様の贖いの死しかない。死んだ私が生きる道はここにある!」それに気づいた人は命を得て、試練にも脱落せず残ります。実は、ルカ8章10節の言葉は、イザヤ6章10節のイザヤの召命の時の反語的な招きの言葉だったのです。
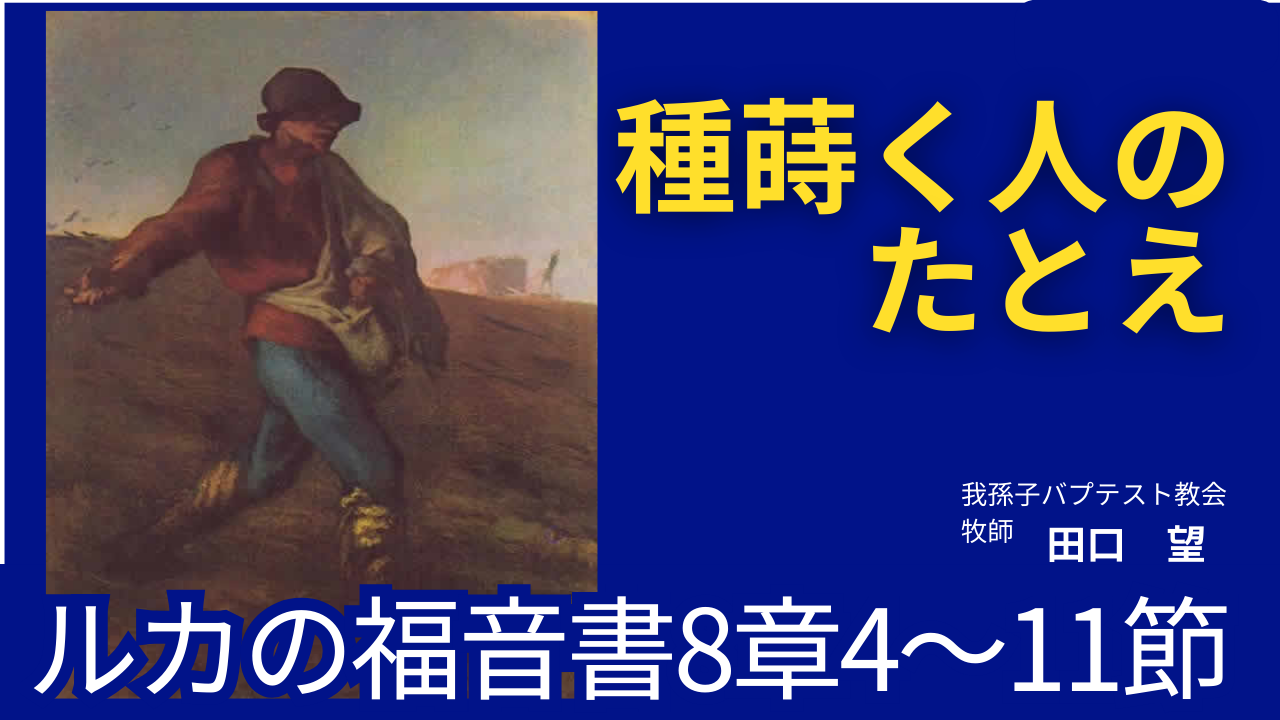


コメント